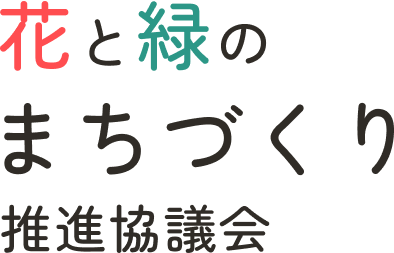Newsお知らせ
花ごころ 平成14年秋号

テーマ:秋の七草
なぜか全部をすらすらと思い起こせる人は少ないようです。春は躍動的で生活に密着している種類に対して、秋は物静かな侘び寂びの世界が連想されるからでしょうか。
山上憶良が詠んだ「萩の花、尾花、葛花、罌麦の花、女郎花また藤袴、朝貌の花」が万葉集に載せられており、広く認められた秋の七草とされています。昔の人はなんと素朴な花を愛したものよと思われますが、現代の派手な花は、草花はもとより花木も含めてその後に渡来した外国産で日本古来の夏から秋に咲く花はこんなものだったことに気づかされます。いま世界的に生物の地域固有種の保存が叫ばれていますが、人も物も地球をかけめぐる時代、ことの善悪は別にして容易でないことはこの事実からもわかります。
ハギはいまも健在、6月に切り戻し挿し木をすれば、低い丈で鑑賞できます。尾花のススキは丈夫なやっかいもの、しかし、人の手の入った土地にだけ生える不思議もの。クズのつるはよく見かけるが花はなかなか見られない。
別名を美しく忍耐強い女性にたとえたヤマトナデシコは意外に野生に耐えられなくなり、鉢植えは毎年植え替えないと溶けてしまう。オミナエシは大きな芽で冬を越した茎だけに花をつけるので植え替えは花後すぐに。葉が3枚に別れているのがフジバカマ、1枚葉は親戚のひよどりばな。アサガオはキキョウのことらしく、早春に種をまけば秋には咲きます。なお、今の朝顔は後の渡来種です。