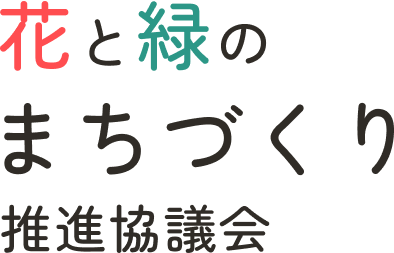Newsお知らせ
花ごころ 平成16年春号

テーマ:カタクリ
染井吉野桜より半月も前に咲きだす野草で、カタクリほど豪華でしかも集団で咲く花はほかに見当たりませんが、古事、伝説のどこにも出てきません。自生環境が限定されていて人目にふれにくかったせいでしょうか。 ユリ科カタクリ属、日本の中北部から亜高山帯、朝鮮からサハリンまで分布するといわれ、同属では黄花や白花の種類が北米合衆国からカナダ南部に10数種類が自生するそうです。名称は、球根が栗の実の芽を出したときの片方に似ているという意味らしい。 はじけたばかりのタネの頭のほうには白い肉質の帽子を被っており、特殊な芳香を出しているので、アリがせっせと巣の中に運びます。しかし食べられることなく発芽に快適な場所に収まる、という一種の詐欺だがアリに大きな迷惑はかかりません。驚くべき自然のしくみには関心させられます。1年目の葉は細い棒状、小さな縦長の球根(鱗形)をつくり、毎年、新しい球根に作り替えながら地下にもぐっていきます。苦手な高温や低温、乾燥から身を守るためですが、地中は空気不足になりやすいため、砂礫がくずれて木の葉と堆積したような場所や似たような条件にしか自生しにくいことになります。 地上の生活は年間70日ほど、なんとも効率がわるく開花までに10年近くかかるのを知れば、球根から片栗粉を採ったり、葉や花のおひたしを食べる勇気はなくなります。