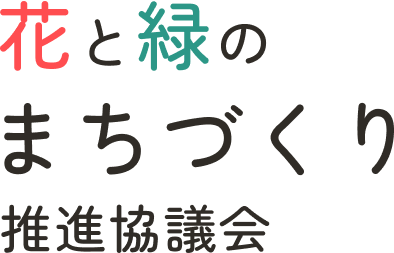Newsお知らせ
花ごころ 平成16年夏号

テーマ:バラ
紀元前十数世紀、中東で始められたばらの愛好は、ギリシャ時代にすでに美のビーナスと深い関係になり、11世紀に西洋に持ち込まれてからも美の象徴として数々の神話、伝説を生み出します。ただ、花を栽培側から観賞する癖を持つ山さんには、衣に隠れる棘が気になるのですが、歴史的美の前には、むしろ援護刺激?なのかも知れません。 ばら科のばら属の原種はアジア大陸を主に北半球に約120種、このうち現代ばらの親は8種あまりとされ、特に中国の庚申(恒春)ばらが交配されて四季咲きに、同じく純黄色も19世紀に入ってからで、改良の元祖は中国であったのかも知れません。 さて、改良で残るのは青いばら、すでに他の植物からの遺伝子組み換えで名乗りを挙げているのもあり、21世紀はどんな色に仕上がるのか興味は尽きません。 雨の少ない地域で幾世紀も改良を加えられてきたばら、日本では病害との戦いが栽培の基本といえます。温室では全く発病しない黒星病も、露地では丸坊主に落葉してしまうこともしばしば。農薬は予防ですから、数日ごとにどれだけ続けられるかで決まります。 四季咲き種は株元から次々に枝(シュート)を伸ばし、古枝は年ごとに活力を失うので、4年生以上の枝を温存しないで済むぐらいのシュートの発生を確保することが重要で、そのためには根に十分な空気を供給できる土の管理が決めてになります。