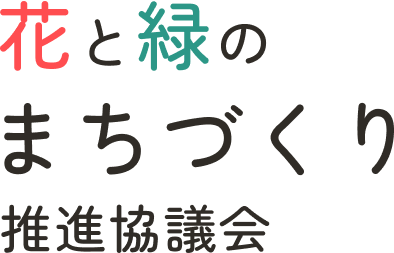Newsお知らせ
花ごころ 平成19年秋号

テーマ:菊
キク科の植物は、アブラナやサクラのように花弁が分かれて何枚か着いているのと違って、アサガオのように全体が1枚に繋がっているグループに入ることをご存知でしょうか。
キクの花を1個の花として見ると、そうは見えませんが、実は茎の頂上にたくさんの小さな花が集まったもので、1枚の花弁は1個の花の花弁なのです。
今から300年ほど前に、中国から中輪咲きほどに改良されたものが渡米したといわれ、その後日本での改良が目覚ましく、花の大きさは言うに及ばず、形や花弁の太さ、長さはもちろん、青を除くあらゆる色、5月から12月までに自然開花する品種など、あの貧弱な野菊から改良されたとは到底思えない現代のキクが生まれたのです。花の改良でもこれほどの変化は類例がなく、これは日本が世界に誇れる文化遺産です。花持ちのよさと冷蔵保存が効くことから仏花として盛んに利用されるため、一般への利用を敬遠する人もいますが常識不足の感情論で文化遺産を泣かせるのはもったいない話です。
宿根草ながら、株のままでは密集と丈の伸び過ぎ、株の老化、ネグサレセンチュウの被害でまともな花は望めません。5~7月の挿し芽で株をリフレッシュ、このうち遅いほど丈が低く小型で若々しく咲かせられます。もっと広い利用を工夫したいものです。