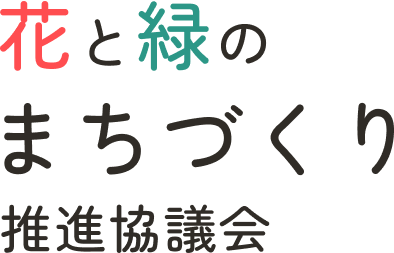Newsお知らせ
花ごころ 平成20年度春号

テーマ:ツバキ
春咲きながら和装の麗人、控えめな美しさだ。木へんに春は、漢字ではなく合成の和製文字だそうで、日本に自生し、古くから親しまれてきたことが伺えます。語源とされる厚葉木、津(艶のある)葉木は納得できるのですが、調べの過程が興味あるところです。山口県から新潟県までの日本海岸にユキツバキ、九州から宮城県までの太平洋岸にヤブツバキがあり、内陸部や東北北部には自生しないことから耐寒性の限界がみえます。これらの自生種から変わりものが発見され、西暦1650年頃にはすでに100を越える品種が記録されております。ただ、日本には常磐木(ときわぎ=常緑樹)には「神が宿るといふ」土俗的な信仰があり、同じツバキ科の榊がいまでも神事に用いられていること、出陣や祝い事には嫌われたことが今でも一部に残るように、時代によって有形無形の制約があったようです。
西日本に自生するサザンカは近縁で、花弁がばらばらに落ちることで区別できるが、カンツバキ、ハルサザンカなど両者の交配種や中国系も入って今は大変にぎやかです。
旺盛に育ちますが剪定には強く、5月と真夏を除き、枝先を詰めるより強い枝を幹近くから抜き取るようにすると、幹から小枝が離れず、いつも同じ姿を保てます。移植は9月が最良。挿し木は、6月から9月まで、1年目の冬は保護が大切です。