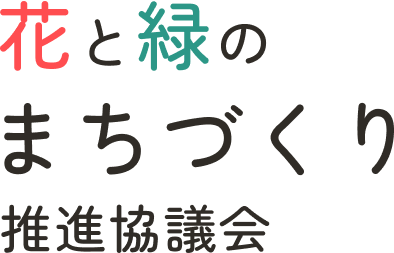Newsお知らせ
花ごころ 平成22年冬号

テーマ:キダチアロエ
この和名よりは、別名「医者いらず」の方が知られているかもしれません。胃腸薬、やけど、化粧品などに利用されているのは周知のとおりですが、日本薬局方では緩下剤として便秘薬の効能のみが登録されています。園芸好きの中高年の方は、一度は手にしたことがある多肉植物でしょう。
ユリ科アロエ属は、アフリカ大陸と周辺の島に300余りの仲間が自生しており、直径5cmの株から10mの大木になる種類まで千差万別。しかし、薬効としての苦味成分に強弱はあるが、ほぼ共通して含むようです。一時、シンロカイ(別名ベラ、大葉で茎が立たない)種類も売り出されていましたが、栽培のしやすさではキダチアロエに及びません。
観賞と薬用を兼ねて2~3鉢栽培しておくと極めて便利で、特に便秘ぐせのある方には、ぜひお薦めです。株を傷めないよう下葉から取り、皮ごと1回分10~20gほど、苦味隠しに工夫するむきもありますが、良薬は口に苦し、そのままかじるのが安直で、苦味はビールの兄貴分ほど、水ですすげば後には残りません。自然で爽快な明日が約束されます。
栽培を続けるには観賞価値を保つことが大切です。春先に太めの枝先を20~30cmに切り取り、大きめの鉢に挿してそのまま日当たりのよい戸外で育てれば、初冬の取り込む頃にはいい姿で花穂が出てきます。凍結しない条件なら少々の灌水も続けます。