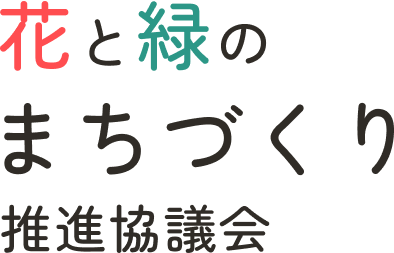Newsお知らせ
花ごころ 平成26年冬号

テーマ:カーネーション平成26年冬号
30年も前の話しですが、真夏に花弁が顔を出し始めたばかりのつぼみの切り花が、長野県から東京市場に出荷されました。ところが、花屋さんにわたってからも一向に花は開かず、初恋の花に終わってしまったのです。その後の研究で、密閉された保冷車でリンゴと一緒に輸送されリンゴから出るエチレンガスにより開花しなかったことがわかりました。
エチレンは植物の休眠や成熟、老化などに作用することが知られていますが、カーネーションは、リンゴばかりでなく自ら出すエチレンによっても老化を速めていることがわかったのです。そのころ開発されたエチレン抑制の水揚げ剤によって、1週間の花持ちは、2週間に伸びたのです。生産者の水揚げ処理による花持ちの倍加は、需要の拡大が期待されましたが、なんと、日もちが倍になれば生産は半分で済むこと。恩恵は流通業者と消費者が受け、その後、世界の生産面積は半減してしまったのです。
カーネーションは欧州から中近東に自生するナデシコ類が交雑されて徐々に発達し、中国のセキチクが加わって四季咲き性になったといわれます。 どの時点でカーネーションと呼ぶようになったのかは諸説あります。

母の日の贈答用には、切花に加え鉢物も多くなりましたが、葉や茎の表面の蝋質は、強い日射しと水不足にも耐えるための備えですから、反対の置き場(日陰)の管理では美しさを発揮できません。