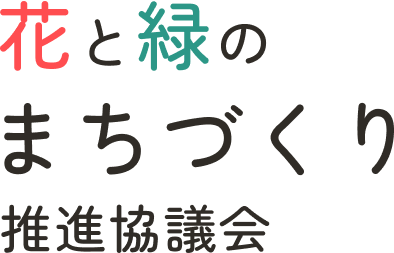Newsお知らせ
花ごころ 平成26年夏号
テーマ:ニチニチソウ
夏の花壇を賑わす草花の中では先輩格で、昭和初期の園芸書で、春播き草花15種ほどの解説があれば、必ずと言えるほど載っていました。施設や農薬もない炎天下で平然と花を続ける頑丈さは、お盆の切り花として大変重宝だったのです。また、整った照り葉の上に次々咲く花は3~4日しかもちませんが、萎む前にスッポリと抜け落ちて、後から咲いた花の観賞を邪魔しない性質は現代の花壇用としても適任でしょう。
マダガスカル原産のキョウチクトウ科、当初はツルニチニチソウと同属としてビンカと呼ばれていましたが、その後カタランツス属として独立しました。日本で古い花の歴史を尋ねると必ず薬草に突き当たるのですが、本種も、花木のキョウチクトウほどではありませんが、全草に毒性があり、世界的に民間薬として利用されていたようで、多くの薬草書には、胃潰瘍、消火促進、便通に用いるとあります。昭和30年代には悪性リンパ肉芽腫の抑制効果が報告されて注目されたが、その後あまり発展はしなかったようです。我々にとっての毒性、薬効も、植物には食害等から逃れる懸命の抵抗なのでしょう。
熱帯の自生地では低木となって咲き続けるようですが、日本では1年草として夏から霜の降りるまで観賞します。移植や根詰まりなど根を傷めると復活が容易でないので、直播きかポット育苗とし、定植後は観賞期間が長いので肥料切れのないようにします。